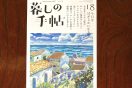『ある、りんご園の一年』が届きました。
ものすごく心揺さぶられる本でした。これを、どんな言葉で伝えたらいいかわからなかったので、そのまま江利さんの言葉を引用させてもらいます。
写真と文は木村江利さん。
自然栽培でりんごをつくってきた木村秋則さんの娘さんです。『奇跡のリンゴ』の木村秋則さんはご存知の方も多いのではないかと思います。
その秋則さんの隣で、共に栽培してきた江利さんの視点から、自然栽培でりんごを育てるというのがどういうことなのか、が描かれた本。日々りんご畑に向き合う中でしか、出てこないと思われる言葉ばかりでした。
許可をいただき、以下、引用です。
「自分が手を出せない世界を知ること」「自然に癒されるのではなく、許されるという感覚」「無力さを知ることで許され、生きる活力が生まれるのではないだろうか」「秋はつらい。もはや秋は収穫ではなくりんごを燃やす時期となりました。」——————日本のりんごは改良に改良を重ね、それは農薬ありきで勧められているものなので、自然には馴染みません。
:
山間地で十数年放置されたリンゴ畑が、どんなに朽ち果てても、周囲の自然とまったく馴染んでいないのを見た時に、栽培である限りは良いことをしているわけではない。結局はエゴなのかもしれないとも思いました。
:
「自然」「栽培」とは、自然の力を借りて栽培すること。しかし、自然の力を借りて育てられているのは作物ではなく、私たち人間の側のような気がします。自然という大きなものの中で自分を知り、この命で関わり、生きることを育てていく。それが自然栽培なのかもしれません。———異常気象にあってうちの畑だけがノアの方舟のように救われることはなく、むしろ先陣を切って影響を強く受け沈んでいきます。自然は自然以上のものをつくらない。つくれない。
——————
『自然栽培』に記事を書かせてもらっていた頃、都度、頑張って書いているつもりだったけど、なんにもわかっていなかったんだなと思わせられました。
あの頃の自分にこの本を見せたい。
温野まきさんの時雨出版の新刊
山下リサさんが装丁・デザイン
@kkounousya



追記:
こちらの投稿、わたしが言葉にばかり着目しすぎて、「写真集+ことば」だからこそ伝わったという点をきちんと書けていなかったので、少し追記させてください。この本は、江利さんが四季を通して撮った畑や木村さんの写真が掲載されていて、その間に言葉が挟まれている本です。わたしが「写真+言葉」の間の、おもに言葉にがーんとやられて、偏った投稿になってしまっていたかもしれません。字面だけを、ここに抜き書きしてしまいましたが、これらの言葉は、写真の間にあってこそ生きる気がします。伝え方の問題でした。
あれらの写真の間にある言葉だから生きているってことを、最初に書くべきでした。いずれにしても、本で見ていただけたら、何の説明もいらないものだと思いますが。

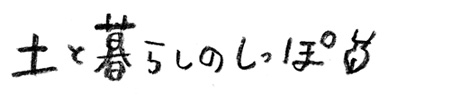

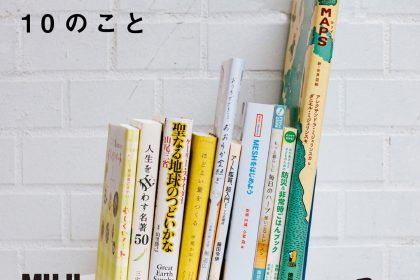




![[記事公開] 石見神楽の広がりに驚愕して。ニッポン継ぎ人巡礼第3回](https://kaikaori.com/main/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/2206-featured-132x88.jpg)